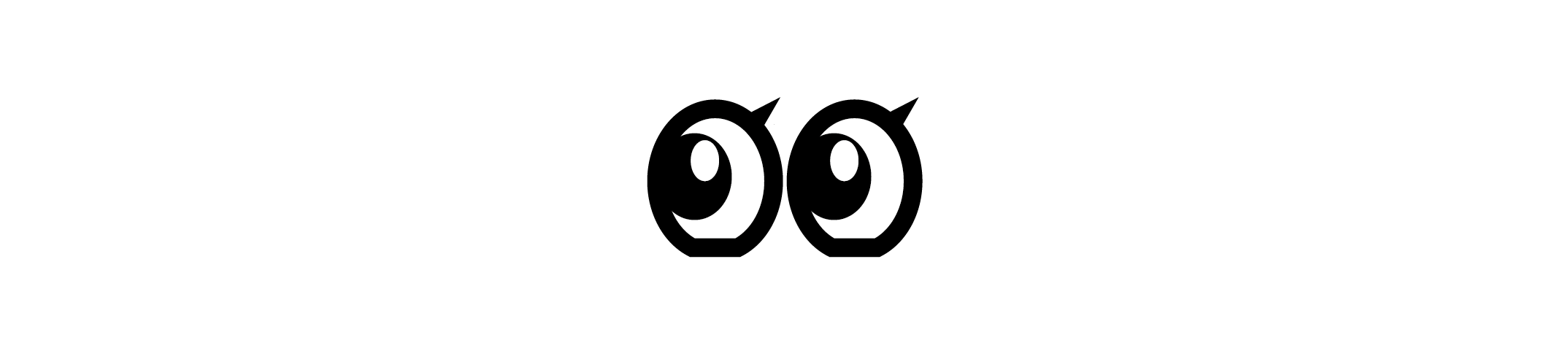本記事では主にセミナー、講演、ディスカッションを中心に紹介する。
モーニングセミナー
司会は遠藤俊吾氏(福島県立医科大学会津医療センター)。
1)大腸癌死亡/発生の抑制をめざして
新しい内視鏡 FUSE colonoscope の有用性と限界
今井健一郎氏(静岡県立静岡がんセンター)による講演。大腸内視鏡の目的は大腸癌の発生と死亡の抑制である。今井氏は、スコープの先端に二つのレンズを備えた超広視野角大腸内視鏡(FUSE)が腺腫の見逃しを減らす可能性がある、と述べ、静岡がんセンターにおけるFUSEの臨床での使用経験を報告した。また、大腸内視鏡の精度管理にADR導入を行うべきとも述べている。
2)大腸カプセル内視鏡検査について
渡部宏嗣氏(若宮渡部医院)はカプセル内視鏡検査(CCE)のe-learningや読影支援システムについて紹介。CCEが未だ症例数が十分とは言えないなかにあって、日本カプセル内視鏡学会の提供するe-learningは初学者のCCE読影能力の向上に有効である。また、若宮渡部医院ではCCE読影支援を行っており、29施設にサービスを提供している。渡部氏は、今後のさらなるエビデンスの蓄積により、CCEが大腸診断の一翼を担うことが期待されると結んだ。
パネルディスカッション1
司会に平山眞章氏(斗南病院)、岩月建磨氏(松田病院)迎え、本邦における大腸CT検査の精度検証をテーマに、6名の演者による報告とディスカッションが行われた。本記事では、モーニングセミナー・パネルディスカッション・教育講演などを中心に報告する。
永田浩一氏(国立がん研究センター 社会と健康研究センター)は日本初の大腸CT検査の精度検査として公表された、大腸腫瘍検出能の非劣性試験「Japanese National CT Colonography Trial(JANCT)」結果から、本邦の大腸CT検査の精度は欧米の臨床試験と同様に高いことが証明されたことを報告。標準的な検査法を理解し、施設間の精度のバランスを最小限にすることで、患者に最適な検査を提供することが可能としている。
歌野健一氏(福島県立医科大学 会津医療センター)は低用量前処置を用いた大腸CT検査の精度評価を行い、通常前処置大腸CT検査同様に良好な結果が得られたと述べた。その理由として、タギング、撮影および読影などで、これまでに得られたエビデンスに則って大腸CT検査が行われたことが理由として考えられるとしている。
龍 泰治氏(市立砺波総合病院)は大腸CT検査で異常が指摘され、内視鏡検査が行われた症例を振り返り、大腸CT検査の精度を検討した。砺波総合病院でのCT読影レポートの分類C-RADS C3もしくはC4の症例(計46例)のうち31例に対して内視鏡検査が行われ、18症例で癌が発見された。同氏は少しでも疑わしい症例を分類していたC3の陽性的中率が低いが、やむを得ないように考えている、と述べた。
丸山 健氏(NTT東日本伊豆病院)は同院での大腸CT検査が精度検証によって精度が担保されている検査手技を用いることで、検診目的として良好な結果が得られている。大腸CTによる検診を中心に行っている施設のため、他施設に依頼している内視鏡検査の受診率や未把握率が今後の課題である。
伊山 篤氏(榊原サピアタワークリニック)による、Dry変法による任意型検診大腸CT検査の妥当性の報告。受診者の負担が少ないDry変法は、全体の約30%に固形残滓が見られるが、タギング能は良好で、2D画像による読影は可能である。受診者に対しては、3日間にわたる造影剤の服用などへの理解と実践が重要になる。
藤原正則氏(亀田メディカルセンター)は同施設の人間ドッグの大腸CT検査において、より精度の高い大腸癌検査を行うため、便潜血検査を合わせて施行している。そのデータをもとに検証を行った結果、同施設の大腸CTはJANCTと同等の診断精度が得られていること、大腸CTは6㎜以上の病変で大腸癌検査のモダリティとして十分に期待できる検査であると見られている。
教育講演
司会は野崎良一氏(大腸肛門病センター高野病院)、講演は島田剛延氏(宮城県対がん協会がん検診センター)。
大腸がん検診 最近の話題
2016年は大腸癌検診における大腸CT検査の位置づけが、2つの視点から話題となった。1つは精密検査法としての位置づけである。日本消化器がん検診精度管理委員会から「精密検査を前大腸内視鏡検査で行うことが困難な場合は、大腸CT検査あるいは、S状結腸内視鏡検査と注腸X線検査の併用のいずれかを実施する」という提案がなされ、大腸CT検査が広く実施されるようになることが予想される。それに伴い、正しい前処置法・撮影法・読影法を普及させることが今後重要となってくる。
パネルディスカッション2
司会は木島茂喜氏(自治医科大学)と安田貴明氏(長崎県上五島病院)。大腸CT検査における偽陰性病変とその対策をテーマに貴重な症例の報告とディスカッションが行われた。
平山眞章氏はJANCT症例における大腸CT検査偽陰性病変の検討を行い、消化管CT読影では病変の高さの差が見止まられる病変は指摘されやすい一方、高さの差が少ない病変は指摘しにくいことを指摘。読影では平坦型病変の存在診断は難しく、偽陰性病変となりやすいことを念頭に置くべきであると述べた。
永田浩一氏は多施設共同試験UMIN6665に基づき、偽陽性病変の特徴と対策につて説明。タギング残滓内病変は丁寧に2D読影をすること、多発病変症例に対しては読影バイアスの存在を自覚すること、バウヒン弁の同定を確実にして病変と鑑別することなどを、症例画像を交えたうえで、大腸CT検査の検出限界があることを述べ、注意をうながした。
神子枝里子氏(亀田メディカルセンター)の報告は下部直腸・肛門管についてである。同院における当該領域の偽陰性症例の原因として内痔核と判断したことやバルーンによる圧排、隠蔽によるもの、また異常な石灰化を認識できなかったことにあると考察した。そのうえで、肛門から下部直腸病変を意識して撮影、読影することが重要と考えている。
清水徳人氏(まつおかクリニック)は一度大腸CT検査で病変無しとされた1年4ヶ月後に2型腫瘤を指摘された症例を示し、偽陰性病変をなくすためには、タギングは必須、拡張不良も原因となりうるため可能な範囲で拡張良好画像を目指すべきであるとした。また、大腸CTは適切な検査で得られた画像を十分なトレーニングを受けたものが読影すれば偽陽性は少ない検査であるが、フォローアップの検討は必要と考えられるとも述べた。
加藤貴司氏(市立稚内病院)氏は大腸CT施行の3年後に進行大腸癌が判明した症例を経験した。その検討から、大腸CTにおいても、いわゆる中間期がんが存在し、検査の普及が進めば、重大な課題の一つとなりうると指摘。その対策として、多施設でのさらなる症例の蓄積が必要としている。
本田徹郎氏(長崎みなとメディカルセンター市民病院)は全大腸内視鏡検査と大腸CT検査で指摘されなかった進行大腸癌の症例を示した。検査の2年後に深達度SS、大きさ11㎜のType2の進行大腸癌が発見されたが、その後の検討から初回検査時には存在しておらず、急速に発育した可能性が高いと考えられた。同氏は、大腸CTは本症例のように後向視的かつ客観的な評価が可能であるという特性をもち、それにより大腸癌の1つの自然史を追うことができたと述べた。