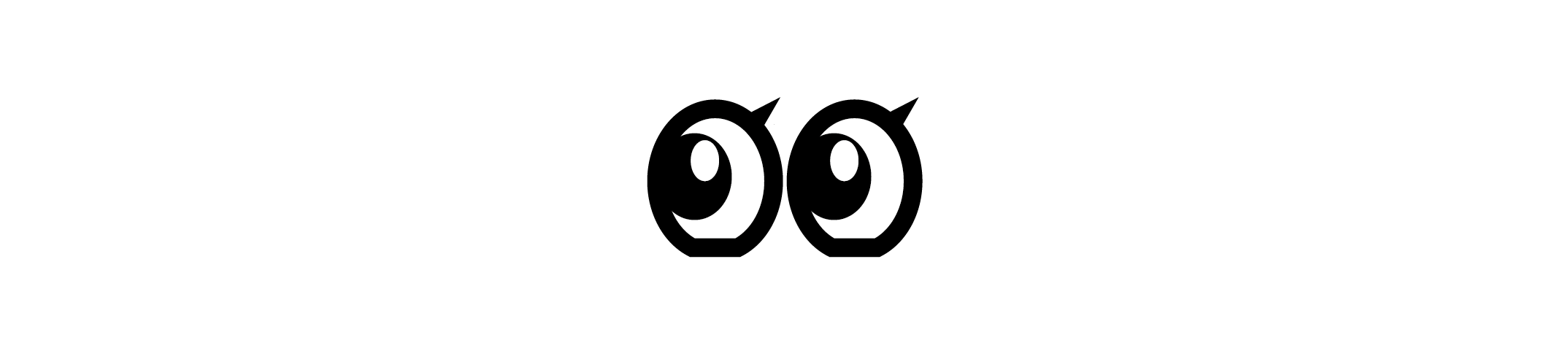第13回消化管先進画像診断研究会が9月9日(日)、大阪国際交流センター(大阪市)にて開催された。当番世話人は永田浩一氏。同氏は開会にあたりまず北海道地震に触れ、犠牲者を悼むとともに、お見舞いの言葉を述べた。今回は、1.「大腸検査(CT/内視鏡)の標準化に向けて!」、2.「画像診断におけるAI(人工知能)の現在と未来」の2つのテーマを掲げ、5部構成で行われ、最新情報が習得できる充実した内容となった。
モーニングセミナー
遠藤俊吾氏(福島県立医科大学)司会のもと、尾田済太郎氏(熊本大学大学院生命科学研究部)が、「大腸癌診療におけるX線被ばく低減の考え方と実践」と題し、講演を行った。放射線診療(医療被ばく)の大原則として「行為の正当化」と「防護の最適化」、つまり「適切な検査適応」と「X線被ばくの最適化」が重要であるとし、「適切な検査適応」についてはエビデンスに基づいた明確な検査目的の設定が必要であり、「X線被ばくの最適化」については国際放射線防護委員会(ICRP)が提唱するALARA(as low as reasonably achievable)の原則に則る必要があるとした。わが国の医療は「検査目的」の設定が曖昧であるとも指摘し、求めるべきは「検査目的に必要十分な画質」であって「最高の画質」ではない、と訴えた。
次に、「AIによる画像診断支援の取り組み」について白旗 崇氏(日立製作所ヘルスケアビジネスユニット)が講演し、現在、AIブームが起こっている背景として、センシングデバイスが進化しビックデータの取得が可能になったことや、計算環境の飛躍的な性能向上、ディープラーニング技術の進歩などを挙げた。同社も心疾患患者の再入院リスクの予測や、画像診断支援による診断効率や質の向上のために、ディープラーニングをはじめとするAIの活用を進めているが、ディープラーニングには、学習のために膨大な量のデータが必要であることや、演算ロジックがブラックボックスで結果の出力根拠が不明であるなどの問題があるという。本セミナーでは、ハイブリッドラーニングのコンセプトや、AIを用いた医用画像診断支援に関する取り組みを紹介した。
大腸CT検査の標準化に必要な知識
司会は、木島茂喜氏(自治医科大学附属病院)と藤原正則氏(亀田メディカルセンター幕張)がつとめた。「標準的前処置法」について高林 健氏(北海道消化器科病院)が解説する予定だったが、北海道地震の影響で来場できず、急遽、安田貴明氏(長崎県上五島病院)が高林氏に代わって解説した。大腸CT検査の腸管前処置は、検査精度を担保できる適切な方法を実施することは無論だが、検診や精密検査を目的とする場合には、できる限り前処置負担を軽減し受容性を向上させることも重要であると述べた。
次に、「標準的検査(腸管拡張・撮影条件)法」について、岩月建磨氏(松田病院)は、大腸CT検査において腸管を十分に拡張させ撮影することは、前処置と並び非常に重要で、診断精度に大きく関係するため、しっかりと拡張させることを心掛ける必要があると述べた。さらに、自動炭酸ガス送気装置を用いることにより安定した拡張が得られ、また保険診療上自動炭酸ガス送気装置を用いることが必須となっているとした。撮影条件に関しては、2体位共に低線量撮影、1体位のみ低線量どちらでも構わないものの、AECと逐次近似応用を用いた被ばく低減に努めることが重要であると語った。
続いて、馬嶋健一郎氏(亀田総合メディカルセンター)が、大腸CT検査の読影方法について、第一に体得すべき「標準的読影方法」を述べた。3Dと2D画像を一通り読影する方法を示し、3D画像は襞上の病変や小さい病変を発見しやすい利点があり、2D画像は水没領域や拡張が悪い部位を観察するのに必須であり、両画像を読影することで見逃しを防げると解説した。デジタルクレンジングは、病変が飛んでしまうなど、偽陽性の原因となる可能性があるため、使用しないことを基本とし、実際の読影を行うにあたっては偽陰性、偽陽性になりやすい点についても知っておくべきであると語った。
エキスパートによるワークステーション操作から学ぶ標準読影
~熟練者による基本と読影困難例への対処~
永田浩一氏(国立がん研究センター)と和田幸司氏(NTT東日本伊豆病院)が司会をつとめ、富士フイルムメディカルとAZE社によるプレゼンと経験豊富なプレゼンターによる読影の実演が行われた。まず、安田貴明氏(長崎県上五島病院)が2Dと3Dを使って2症例を実演し、残渣が多い場合の3Dでの判別の難しさや確定するポイントなどを解説した。次に、永田浩一氏が3症例を実演し、2症例目はクイズ形式で行われた。永田氏は、「速ければ早いほど、見落としが多くなる。基本に立ち返って、心配なことは立ち止まって見る」ことの大切さを訴えた。
教育講演
野崎良一氏(大腸肛門病センター高野病院)司会のもと、松田尚久氏(国立がん研究センター中央病院)が、「対策型検診への大腸内視鏡導入に向けた期待と課題」と題して、講演を行った。日本では年間15万人近くが大腸管に罹患し、5万人以上が大腸がんで命を落としている一方、米国に目を向けると、大腸内視鏡検査を主体とした大腸がんスクリーニングの強化により、1980年代から男女ともに大腸がん罹患率・死亡率は減少傾向に転じている。米国の最近20年の動向とNational Polyp Study(NPS)の結果から、TCSおよび内視鏡的ポリープ摘除が大腸がん死亡率の減少に大きく寄与したことは疑う余地はないものの、松田氏らが実施した離島をモデルとしたTCS介入研究(新島・大島 Study)では、TCS検診を無料で提供できる環境を整えても、対象とした40~79歳の全住民の中で3年間にTCS検診を受検した者は30~45%だった。つまり、日本において対策型検診へのTCSが可能になったとしても、どれだけの対象者がTCSをきちんと受検するのかといったアドヒアランスの問題があると、問題提起した。最後に大腸がん検診の課題と将来への期待として、①検診受診率・精検受診率の向上への具体的な方策が必要、②住民票ベースの検診データベースの作成、③大腸内視鏡検査を対策型検診(便潜血検査)にどのように組み込むかの議論とその体制整備、の3つを掲げ、講演をまとめた。
特別講演
教育講演に続いて、野崎良一氏が司会をつとめ、多田智裕氏(ただともひろ胃腸科肛門科)が「世界に挑戦する日本の内視鏡AI」というテーマで講演した。多田氏は、2015年2月にAIの画像認識能力が人間を上回ったとし、AIは医師の道具であり、AIを使う医師とAIを使わない医師では大きな差が生まれると警鐘を鳴らした。また、多田氏のチームは、ディープラーニングを用いたAIを内視鏡画像に応用して、内視鏡専門医並みのピロリ菌胃炎の人工知能診断および、胃がん拾い上げ人工知能診断に世界で初めて成功しており、その内容も紹介した。さらに、研究使用目的ではあるものの、すでにがん研有明病院、大阪国際がんセンターなどの施設で稼働しており、それらの事例、動画リアルタイム診断のデモなども紹介した。
パネルディスカッション
「正診に至らなかった大腸CT症例から学ぶ」のテーマのもと、司会を松本啓志氏(川崎医科大学附属病院)と岩野晃明氏(徳島健生病院)がつとめ、西川昭則氏(東近江市蒲生医療センター)、田中順子氏(市立大津市民病院)、北井孝明氏(舞鶴共済病院)、三上恒治氏(住友病院)、小阪寿幸氏(高石藤井病院)、田上修二氏(ほくと記念こやまクリニック)、清水徳人氏(まつおかクリニック)、奥田晃英氏(中井記念病院)の8名が講演とディスカッションを行った。それぞれか正診に至らなかった症例が提示され、起こった要因や読影における注意点などが話し合われた。
最後に、野津 聡氏(埼玉県立がんセンター)より閉会の挨拶とともに第14回消化管先進画像診断研究会の開催についても発表された。次回は東京にて2019年3月10日に開催される。