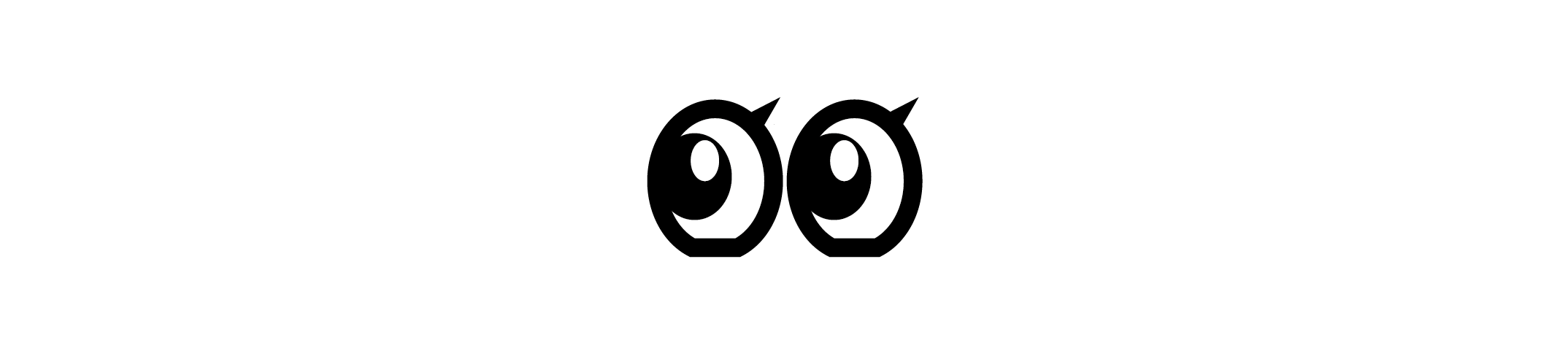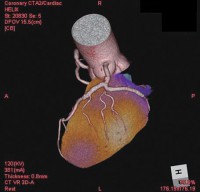時代の先を行く画像処理技術 ziostation2 & PhyZiodynamics
最先端の画像診断をいちはやく導入する熊本中央病院。同院ではザイオソフト社の新技術に着目してziostation2の運用を開始した。同社の新しい画像処理技術“PhyZiodynamics”(WIP)の検討も進めている。その実績と新たな可能性について、放射線科部長の片平和博氏と診療放射線技師(核医学担当)の泉 英伸氏にお話を伺った。
高精度の融合画像診断を身近にする
CT/SPECT心臓フュージョン
近年、高い性能を持った画像診断装置の普及により、心臓検査は形態画像のみならず、機能画像による評価も増加してきている。なかでも心臓CTによる冠動脈の走行や狭窄部位の確認など形態評価に加え、心筋血流SPECTなどによる機能的情報を融合させる手法が注目されている。両者を組み合わせることにより正確な虚血部位と予後、治療方針などの決定に大きな役割を果たすことができる。
正確な位置合わせを可能にする
放射変換アルゴリズム
熊本中央病院でのCT/SPECTフュージョン検査では、一体型装置によるハードウェア・フュージョン、撮影後にワークステーション(WS)を用いたソフトウェア・フュージョンの両方を行っている。泉氏によると、「特に心臓領域、血管の走行を明瞭にする診断の場合は、ziostation2の“CT/SPECT心臓フュージョン”を用いたソフトウェア・フュージョンで行っています」と説明する。
ziostation2によるCT/SPECT心臓フュージョン検査の経験は現在までで30〜40例。「やはり心臓のフュージョン画像が有用性を発揮するのは虚血領域の同定時。とりわけ境界領域、例えば右冠動脈(RCA)、左冠動脈回旋枝(LCX)、高位側壁枝(HL)、対角枝など、確定診断を下し難い領域での責任血管と虚血領域の同定がより容易になります」と泉氏は語る(図1 対角枝(#9)かHLか診断に迷う症例(HLが虚血))。
同院ではこれまでWSで心臓のフュージョン画像を作成する際には、左心室心筋と冠動脈抽出の作業後、SPECT画像との位置あわせをマニュアル操作で行う、といった流れで核医学担当の診療放射線技師が作業を行っていた。ただしSPECTは自然呼吸下で撮影することや負荷による内腔拡大などの影響で、位置合わせ自体が困難な例が少なからず存在していた。結果的に再現性は悪く、位置合わせの信憑性にも疑問を抱かれていた。苦心して得た画像でも詳細な部分では虚血領域やReversibility領域を正しく評価できない症例もあった。
だがziostation2では、煩雑な作業は不要になり、処理時間の大幅な短縮と共に再現性も向上した。決め手は「放射変換法」と「自動処理」である。「放射変換法」はCT画像の心筋にカラーマッピングする際に、ら放射状にマッピングするアルゴリズムである。位置ずれに強い同社独自のサンプリング手法を用いることで、臨床で使用するRI画像のカラーマップをそのままVR画像にフュージョンできる。冠動脈CTと同時表示させれば、RIの情報を正しく表現しながら、責任血管の観察も一目瞭然となる。
高精度な自動化処理で
誰もが定量的な画像を作成
CT画像からの左心室心筋と冠動脈の抽出も、自動化された高精度な処理が非常に短時間で行われている。泉氏は「ziostation2のCT/SPECT心臓フュージョンでは、自動で心筋上にRI画像を張り付け、技師の作業は微調整のみ。その後の処理も迅速です。左室抽出から血管抽出を経てトータルでも10分程度で完了しますので、当日中の外来診療に画像を間に合わせることも可能です。さらに、自動化され再現性の高い作業ができるので、フュージョン画像の作成をRI担当者だけでなく、3D担当の技師と分担することも現実的には可能です」とその利便性を強調する。作業時間の短縮、作業の簡便化は、検査のルーチン化に大きな役割を果たすのである。
片平氏も「冠動脈疾患の中等度狭窄の場合は機能診断を併せなければ、治療の是非は判断できない。虚血性心疾患では、解剖学的に同じ位置の虚血でも、血管の力関係の影響で、現実の責任血管が経験上の判断とは異なることも少なくありません。境界領域であるほど、VR画像上で責任血管と虚血領域を評価できる CT/SPECTフュージョン画像診断によって確実な診断を導くことができます」と高く評価する。
なお、最新版のziostation2では、Stress/ Rest/Reversibilityの表示だけでなく、Washout Rateの表示も実装された。片平氏、泉氏とも今後さらに臨床での有用性が高まることを期待している。
既存の時間分解能の限界を打ち破る超四次元画像PhyZiodynamics(WIP)
同じく同院が運用中の「PhyZiodynamics」。これは、スーパーコンピューターに匹敵する高度かつ膨大な計算を超高速で行える、ザイオソフト独自の全く新しい画像処理技術である。その桁違いの計算能力によりかつてない滑らかな4D画像の観察を実現する。これまでの画像処理の概念を一新する、他に類を見ない革新的な技術である。
PhyZiodynamics
超四次元画像への期待
片平氏は最初にその画像を見た時の印象を次のように語る。「初めて目にしたのは2010年の国際医用画像総合展(ITEM)でしたが、そのスムーズな動態の4D画像に思わず吸い寄せられるようにブースに入りました。かなりの衝撃でした」。
これまでの使用経験を振り返ると「動態を診る検査は全てPhyZiodynamicsの対象といえます。時相情報を基軸にしている領域、例えば心臓では心筋、冠動脈、弁の動態などが詳細に再現できるので、高い利用価値がありますね」と語る。
PhyZiodynamicsを用いた解析では、時間分解能に優れているMRI画像の利用が特に向いていると考える片平氏。「特に弁膜症の閉鎖不全といった症例は、PhyZiodynamicsを使って簡便な操作のみで動きが非常に詳しく観察できるので有用です」。
また、心臓以外の検査での可能性も広いという。その1つが腫瘍の鑑別診断。動きのダイナミック撮影を行ったMRI画像からPhyZiodynamicsを利用して、腫瘍と正常臓器との関係を詳細に評価することで、正常臓器への浸潤の有無が可能になるという。
この他にも、CT/MRIでのperfusion検査にて血液流入のタイミングの違いをより詳細に動的に観察することにより腫瘍の質的診断にも役立つと期待している。「PhyZiodynamicsの動画なら腸全体の蠕動などが自然に再現されます。クローン病であれば、罹患腸管の動きが悪いので、それがより際立って見えます」(片平氏)。
PhyZiodynamicsを
さらに駆使する片平氏の挑戦
PhyZiodynamicsの利用は、同院の撮影方針にも変化を生みだしている。片平氏は「あらかじめPhyZiodynamicsの利用を念頭に置き、動きを診る画像を撮影することを常に視野に入れるようになりました。従来は良い画像が撮れたら、WSで再構成するという考えでしたが、その逆の考え方です」と説明する。
現在、新たな取り組みを始めているのがPhyZiodynamicsを利用した非造影MRAだ。ASL(arterial spin labeling)法を用いて血液を標識し、1秒間隔で血管を非造影ダイナミック撮影したデータをもとにPhyZiodynamicsで血流を再現する。「特定臓器に対する血流到達時間が把握できることで、到達時間から血管狭窄の有無を判別できる可能性があります」と片平氏。MRI検査ならデータ量がさほど多くなく、現実的な処理時間でボリュームの作成、動画の書き出しも行えるため、片平氏は「現時点でもMRI検査との組み合わせにおいては、 PhyZiodynamicsは十分、実用に耐えうる」と評価する。
ziostation2とPhyZiodynamicsという新たな武器を通じた実績は、診断能向上とそれによる患者利益に大きく貢献していると言えるだろう。
|

 泉 英伸氏
泉 英伸氏
放射線科
診療放射線技師(核医学担当)
 図1a:Stress
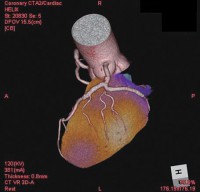 図1b:Rest
 図1c:Reversibility
 - 片平和博氏
放射線科 部長
-
Flashファイル:テキストクリックで拡大
- 図2 PhyZiodynamicsによるmyocardial bridge症例の
Slab MIP表示(CT)
左前下行枝#7にmyocardial bridgeが認められる。心筋の収縮に伴い血管内腔が狭くなる様子が見てとれる。
|