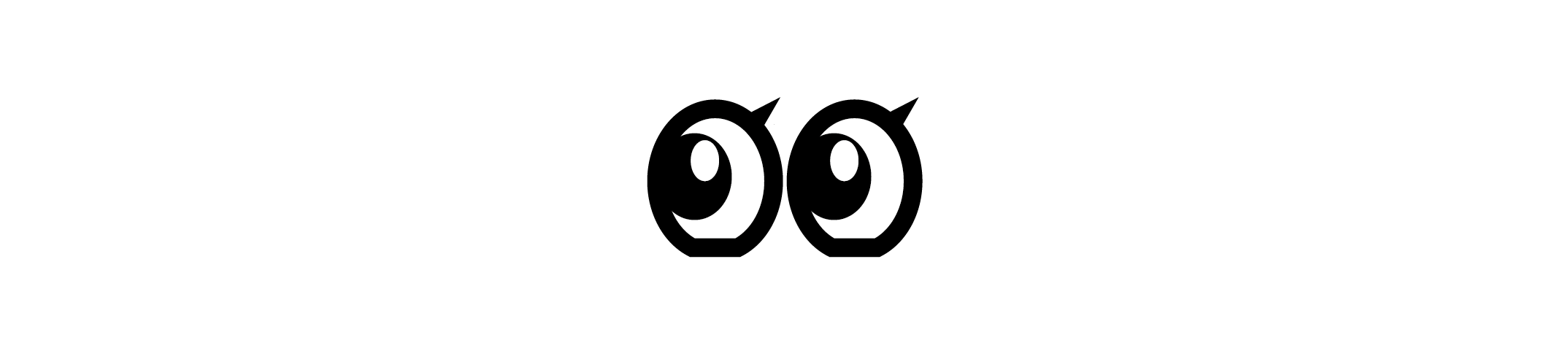SIR2013参加速報
米国東部介在放射線科医
西岡健十郎
はじめに
Society of Interventional Radiology (SIR) 2013に参加したので、速報でお伝えする。「速報」としたのは、SIR2013が例年よりもかなり遅い4月中旬の開催となり、本年は日本医学放射線学会の日程とほぼバッティングしたため、日本からの参加者が極めて少なく、SIRに行きたくても行けなかった方々のためにSIRがどんな雰囲気だったかを伝えることも意味があるかと思ったからである。
従って総論的なレポートとならざるを得ず、観光旅行記に毛の生えた程度のものとなっていることを最初にお断りしておく。プラハ開催のGESTが日本のゴールデンウィーク中に当たるため、もたもたしているとGESTの報告に抜かれてしまい「SIRってのも、そう言えばあったな」なんて思われては、さすがに困るのである。
SIR2013
本年の開催場所はニューオーリンズ。2005年以来の開催場所となった。前回開催の数か月後にニューオーリンズはハリケーン「カトリーナ」の直撃を受けて、海抜より低い位置にあるフランス文化の香り漂うこの大都市は、水浸しの大被害を被ったことをご記憶されている方も多いだろう。避難民の一時待機・非難場所となったのが、Ernest N. Morial Convention Centerである。カトリーナ以降renovateされ、現在、展示場スペースが1.1 million square feet (102,000 m2) 、全体で 3 million square feet (280,000 m2) の広さがあり、メインビルディングの入り口の扉は開いていればどこからでも入れるものの横に長さ1 kmもあるので端っこから入ると、中で延々と歩くハメになる。

さてSIR自体はこの巨大な会場の南西の端の方で、割とこじんまりと行われた。会員数4000名あまりというSIRであるが、何かこじんまりとした感じは否めない。
米国経済の影響がモロに反映される展示場も、前回2005年開催時の勢いはない。これはリーマンショック以降少し持ち直したと言われている米国経済の状況を肌で感じてみればすぐに分かることである。株価が上昇し、失業率も表面的には下がった。しかし以前のようなpensionの良い仕事は少なく、そこには国民の将来に対する不安があっていま一つ活気が戻って来ないのだ。これは株価や通貨の数字だけみていても、またはインターネットでいくら情報を集めてみても分からないことで、やはり自分で足を運び肌で感じることが大切なのだと改めて実感した。もっとも2008年のSan DiegoでのSIR展示場で、資金不足は分かるけれど、展示場がバナナの叩き売りの台のようなチープなものであった頃と比べると相当回復していると言える。


今回のSIRのpresidentはDr. Gary Siskinで、彼の思いきったアイデアと改革が光った。内容自体はとても充実していた。具体的には新しいセッションとはIn the trenches -what I do、Extreme IR、controversy in IR、そして最終日の訳の分からないセッションなどである。従来のfilm reading、scientific session、categorical course、workshopはきちんと残しており、伝統を守りながらも思い切った改革を行って成功したということであろう。最終日にカナダのLindsay Machanが「これまでで一番良かった」と言っていたがまんざらお世辞でもなさそうだ。
私自身はCLI、renal denervation、小児IVR、TACE、radioembolization、IVC filterなどの最新知見を学んだり確認したりして、なるほどと思っていた矢先の4月15日午後、ボストンマラソンでの爆発事件の速報が入ってきた。このニュースを米国で聞くのと日本で知るのとでは、そのインパクトの度合いには雲泥の差がある。この時点ではテロなのか何なのかさっぱり分からない状況であった。
さてSIRに戻ろう。Dotter LectureはDr. Daniel Picusで、日本ではあまり馴染みがない人かも知れないが、IVRに多大な貢献をした人である。Dr. David Kumpeも来ていた。断っておくが米国では誰もが、本人も含めて、Kumpeはカンピーと発音している。誰がどう聞いてもカンピーさんだ。これを日本ではクンペと言うらしいが、きちんと海外に出て、真面目に言語を学んでいただきたい、とお願いしたい。明治時代にはGoehteはゲーテではなくギョエテ、Mozartはモザルトと呼ばれていたらしいが、日本のIVRもクンペ時代ということか。IVRの若い歴史を振り返り、さらに将来を俯瞰するといういつもながらのパターンだったが、ご本人のIVRにかけてきた誇りと愛情に溢れた感動的なスピーチであった。日本でも、日本人によるこういうレクチャーの機会は設けられないものなのか?と感じた。
Film Panel ReadingとBRTO
さて今回は、あまり詳しくレポートされないFilm Panel Readingを取り上げてみたい。これは二つのチームが出てきてテレビのクイズ解答のようなやり方で、次々と提示されるIVR関連の画像に対してコメントしてゆくというものだ。以前は出題者がいて解答者がいて、ひとつの症例をあれこれと深く詰めてゆくやり方を取っていた。日本はいまだにこのやり方を取り入れているが、欠点は症例数を多くできないことである。2時間のセッションで15分ずつとして8例しか提示されない。全米の各施設には年間に十数例以上、症例報告に値する面白い症例があるはずで、これが米国らしくスピード重視のFilm Panel Readingとなっていた。しかしこれでは症例を深く掘り下げる時間がなく表面的となってしまう欠点があるが、drive-inのfast foodの国でもあるし、私は昨年のSIRに参加していないのだが、少なくとも昨年からこのやり方となっていたらしい。
このFilm Panel Readingでは全米の有名な大学から20症例くらいずつ、珍しい症例が提示されるのだが、この“珍しい”症例の中によく、胃静脈瘤にカテーテルが挿入されていて造影されている画像が出てくる。これは昨年もそうだったらしいが、本年もよく“珍しい”として出てきた。しかし逆に言えば、全米あちこちの大学または大きな病院でBRTOが行われている証拠でもある。私は数年前に「BRTO -冬の時代」として本誌にエッセイを書いたことがあるが(西岡健次郎だったと思う)、こんなに早く米国でBRTOが注目される時代がくるとは夢にも思わなかった。やはり正しいものは勝つのである。日本人として嬉しい限りだ。BRTO手技の開発者であり、世界で初めてBRTOを始めた札幌の金川博史先生に早速連絡してみようと思う。

そしてWorkshopで特に際立って目についたのが、BRTOのセッションである。2日目と3日目に開催され、どこも立ち見が出るほどの超満員だった。日本からは東海大学の小泉淳先生がシンポジストを務められ、oral presentationではあのDr. Alan Matsumotoのところに留学して東京女子医大に戻った森田賢(さとる)先生が発表をされた。

米国のIVR医も、『胃静脈瘤からの出血はBRTOで出血を止めて、そのままでもいいが、門脈圧が高くなるのを避けたいならばTIPSを追加する』という当たり前のことがようやく分かってきたらしい。BRTO とTIPSは対立する概念ではないのである。TIPSで胃静脈瘤からの出血をコントロールできないことは明らかで、それでBRTOに注目し始めたIVR医も多いのだろう。「バージニア大学のグループが積極的にBRTOに注目している」とJohn Kaufman教授から直接私が話をきいたのが数年前であるが、そのバージニアのWael Saad教授はBRTOもTIPSもきちんと理解して、政治的なセコい判断に陥らずにこの分野を正しい方向に導いている。
最終日の謎のセッション
さて紙面も限られているので、JVIR awardの非常に政治色の強い偏った選択などはパスして、最後になるが「最終日の訳の分からないセッション topics in embolization」について触れてみたい。これは「IVRの基本的な項目を、IVR界の大御所がレクチャーする」といった内容になっていた。ほとんどの参加者は既に帰ってしまっているような時間帯に、会場はすでに二か所となり、相対的にこの会場はほぼ満員になっていた。James SpiesやJean-Pierre PelageがUAEに関して話し、John Kaufmanがsplenic artery embolizationの講義をしてくれるという豪華版だ。Kumpe(カンピー)先生まで講義して下さった。これは贅沢な限りで私は多いに得をした気分になったが、疑問なのは「ところで一体、これは誰のために企画した講義なのだろうか?」ということだ。繰り返すがほとんどの参加者は既に帰ってしまっている。「大御所が喋り大御所が拝聴する」訳のわからない企画。それもトピックは教科書の目次のようだし。うーむ、謎だ。
このセッションに日本から堀信一先生がIR oncologyとして肺と縦隔のメタに対するIVR治療に関して講義をされ、参加者の多くが話にくぎ付けになっていた。他に、IR navigationでは宮山史朗先生の論文が頻繁に引用され、SpiesはadenomyomatosisのUAEに関して勝盛先生の仕事を引用していた。Miyayama、Katsumoriと日本人の名前が大御所によって連呼されるのは日本人として誇らしい限りだ。是非日本の真に若いIVR医(若手IVR医ではない)たちも科学的なグローバルな良い仕事をしてほしいと思う。ちなみに今回のSIRに日本から招待されていたのは、国立がんセンター病院長の荒井保明先生、奈良県立医大の吉川公彦先生、そしてIGTゲートタワークリニックの堀信一先生だけであった。
おわりに
私は最終日まで参加したが、ある人はAtlanta経由、ある人はSan Francisco経由、またある人はDallas-Fortworth経由で日本に戻ったようだ。私はChicagoで乗り換えがあったが、4月19日の朝のシカゴは小雪の舞う気温34Fの冬景色であった。しかし、空港内は異様な雰囲気で、皆テレビのbreaking newsにくぎ付けになっていた。ボストンの爆破事件の犯人が一人は射殺され、もうひとりが逃亡中という時点の報道であった。WatertownやWalthamには私も友人がいるのでとても心配した。
来年のSIRは南カリフォルニアの南端、San Diegoである。明るい陽射しを浴びて、BRTOがさらに注目され、Film Panel Readingに「珍しいものを見た」としてBRTOが紹介されない日がすぐにそこまで来ているような気がするが、TIPS過激派は全米ライフル協会並みの頑固な石頭であり、まだまだ予断を許さない。ちなみに、私もかつてISET参加記で本誌にレポートしたが、一世を風靡したCCSVIは、どのセッションは客の入りがいまいち、というよりも完全に閑古鳥が鳴いていた。そのうちなくなるだろう。